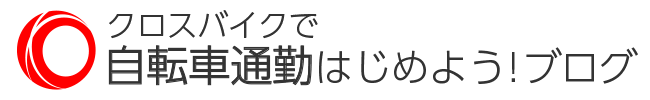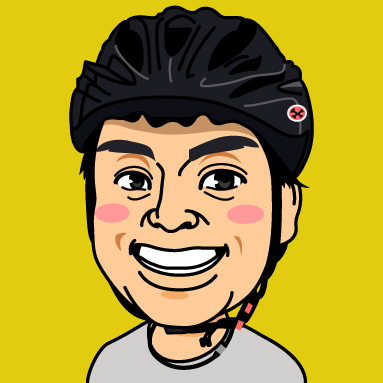2018年6月18日 午前7:58分、最大震度6弱という「北大阪地震」が発生しました。皆さんお怪我などありませんでしたでしょうか?また、自転車通勤中という方もらっしゃったのではないでしょうか?小学生のお子さんやお年寄りの方々が犠牲になってしまい本当に残念でなりません。心よりお悔やみ申し上げます。
今回は、自転車通勤中に地震に遭遇した場合や、地震の時の自転車の使い方についてお伝えしたいと思います。
地震発生時は歩道の右側に
大きな地震でない限り、自転車に乗っていて揺れに気づくことはあまり無いと思います。しかし、大きな地震が来た時は、どのように対応すれば良いのでしょうか。
地震発生時は車道の路肩ではなく、車道の路肩よりもさらに左の歩道に上がり、歩道の右側に止まりましょう。地震発生時には、路肩には車が停車する為に寄って来ます。それは、免許を取るときにそのように教えられるからです。車の運転手も上手に車をコントロールできるかどうかわかりません。パニックになっている恐れもあります。
それを思うと、自転車が路肩に停車すると、車が接近して来て危険です。歩道まで上がるのが良いのでは無いでしょうか。
また歩道から建物の方に近くと、建物から瓦やガラス片、看板などが落ちてくる場合があります。その為建物から距離を取っておいたほうが良いと思います。
これらを踏まえて「歩道の右側にて停車」するのが良いと思います。もちろん、広い公園や駐車場がある場合には、そちらの方が安全性が高いと思いますので、そちらを優先してください。
交通経路が絶たれた時に
また大型地震が発生すると、電車が止まります。電車が止まると移動手段が徒歩ということになり、まずタクシーも捕まえることができないと考えておきましょう。
自転車はその点、移動手段として非常に有効です。阪神大震災の時もそうでしたが、自転車の場合は担いで階段を登ったり、段差を乗り越えたり、平坦な場所では時速20〜30kmで移動することができます。また、キャリーがあれば多くの荷物は運搬することも可能です。子供達を避難させる時も、自転車に子供を乗せるイスが取り付けられている場合、前後に乗せて移動することができます。それに比べて、車や電車は道路や線路に異常があると、途端に身動きが取れなくなってしまいます。地震発生時には自転車が最も有効な移動手段になるのではないでしょうか。
電動自転車で移動する際の注意
「電動自転車」で避難や長距離の移動をする際、注意しなければいけないのはバッテリーの充電です。電動自転車はバッテリーが切れてしまうと突然、鉄の塊のように重い自転車に変わってしまいます。避難時や長距離の移動時に電動自転車を使用する際には、充電器を持って出ると良いのではないでしょうか。あくまで余裕があればという話にはなりますので、緊急の場合には気にせず、すぐに自転車で移動してください。
通常の自転車ではバッテリーの心配はありませんので、長距離で持続的な移動に向いています。前かごやキャリーが付いているシティサイクルは運搬能力も高く、さらに変速ギヤがついていると坂道を楽に登れたりスピードアップもできます。地震発生時にはかなり価値の高い存在になるのではないでしょうか。
まとめ
地震が発生した時には、とにかく身の安全優先してください。特に車道を走っている場合には、車がどのように動くか非常に読みづらい状況になることが想定されます。地震に気づいたら、すぐに減速して歩道に乗り上げて、歩道の右側で停車してください。なるべく建物からは離れてください。
また、道路の地下配管が破損して、アスファルトが陥没している場合もあります。路面にガラス片や砂など想定しない様々なものが落ちていることがあります。地震が収まった後も高速で走らず、路面状況に細心の注意を払いながらゆっくりと徐行運転を行ってください。
地震が起こった時は、心理的にもパニックになりやすく、どのように対処すべきかわからなくなってしまうこともよくあるので、事前にイメージしておくと良いのではないでしょうか。