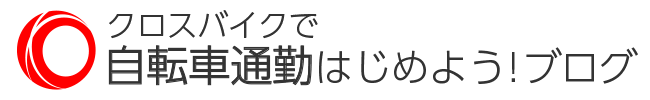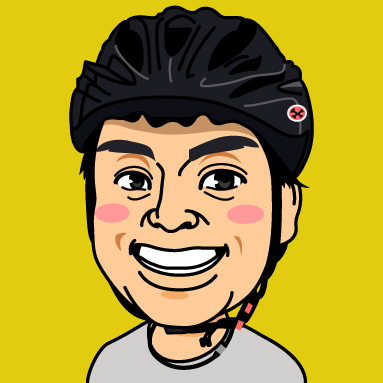先日ホイールをWH-R500からFulcrumRacing5に交換しました。このホイールはワイドリムといってリムの幅が広く作られています。その為、タイヤも25C以上の太さしか対応していません。23Cを装着できないのです。
調べてみると、最近はワイドリムがジワジワ話題に上ってきているようです。僕はこのホイールを知るまでワイドリムについて知りませんでした。そこで今回はワイドリムについてお伝えしたいと思います。
ワイドリムのメリット
通常のリム幅は15Cと呼ばれるもので、リムの内側が15mm、外側が21mmです。それに対しワイドリムは、リムの内側が17mm、外側23mmと2mmずつ幅が広くなっているホイールです。その為タイヤは25C以上推奨となっています。
最近では、23Cよりも25Cの方が路面への設置面積が小さいということがわかってきて、レースでも25C化が進んでいます。さらにワイドリムにすることでタイヤの扁平率を低く抑え、コーナリング時のタイヤの歪みを少なくして、路面との摩擦を少なくしています。
どうやら、タイヤが変形しにくいというのが最大のメリットのようです。それでいて乗り味はマイルドです。23Cの時は、空気圧を7.5barにして乗っていて、結構細かいロードノイズを拾っていました。25Cにしてから、ガタガタという衝撃が随分減り、ハンドルの軽さが程よく安定した感じがあります。ただし、ホイールだけではなくタイヤも交換したので、タイヤの性能差で衝撃がマイルドになったところもあると思います。
実際に乗っていてワイドリムの恩恵をどこで感じるかというと、縁石や、路面の亀裂などの段差での安定感がとても増したように思います。ハンドルが取られそうな「弾かれ感」が少ないという印象です。
今までは25C以上のタイヤは、太くて路面抵抗が大きなイケないタイヤだと思っていましたが、実際に走ってみると速度は変りませんし、減速しやすいかというとそういうこともありません。きちんと空気が入った状態であれば、むしろホイールやタイヤの太さよりも、ハブの性能の方が重要な気がします。
ワイドリムのデメリット
ワイドリムのデメリットとしては、重量が増すという点ではないでしょうか。単純に幅が広がった分、材料が多く必要となります。ヒルクライムなどでホイールを数十グラムでも軽量化したいという場合には、ワイドリムではなく、15Cのホイールが良いのではないでしょうか。
また細いタイヤを装着できないので、タイヤにおいても軽量化が難しくなります。最低でも25Cですから、それぞれのパーツごとの重量増加はわずかであっても、ホイール、タイヤと前後の合計重量で考えると、数百グラムくらいの差になるのではないでしょうか。
ブレーキとのクリアランスが少なくなります。ホイール幅が2mm増加するということは、片面につきたったの1mmなのですが、実際にタイヤをセットしてみると、そのクリアランスの少なさに驚きます。新品のブレーキシューを装着し、ホイールにブレーキシューが擦ってしまう場合は、ワイヤーを引いて固定するなど、さらに開き幅を調整する必要があります。
僕の場合は、ブレーキの左右差を調整するだけでうまくクリアランスを確保することができました。でもブレーキレバーを握ると遊びが少なくなっていて、ペタペタのブレーキシューから新しいブレーキシューに交換した時のように、少し握るだけでグッとブレーキが効くようになりました。
ワイドリムを取り入れるべきか
自転車通勤においては、僕はワイドリムを取り入れるメリットがあると感じています。自転車通勤では縁石や路面の段差、ガタつきが思ったよりとても多いです。また、そのガタつきによってハンドルを取られるようなことがあると、事故につながりかねません。安全性を考えると、安定感のあるホイールの方がやはり良いということになります。
25Cでワイドリムという組み合わせにして見て、一番感じたのは安定感です。安定は安全に繋がるので、自転車通勤では大切な要素だと思います
ロードバイクなど高速域でどのような変化があるのか体感できていませんが、下りでのコーナーなどスピードが出ている状態でコーナリングする際には、安定感が増すのではないでしょうか。